2024年度と25年度、岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム Global Discovery Program(以下GDP)で、1学期間、「ミュージック・アンド・パワー」 という講義をしました。岡山大学のHPによれば、2017年開始のGDPは、「世界中から集まる留学生、帰国生などと日本国内で学んできた学生が集い、英語を共通言語として共に学ぶ国際共修学士プログラム」です。
私は東京藝術大学音楽学部楽理科在学中の1991年に歌手デビューし、卒業後、歌手活動をしながら、瀬戸内海にあるハンセン病療養所と深くかかわるようになりました。2014年に岡山県に移住し、18年から岡山大学大学院教育学研究科で、ハンセン病療養所の音楽文化について研究し始めました。修士論文を一般書として書き直した『うたに刻まれたハンセン病隔離の歴史―園歌はうたう』(岩波ブックレット)があります。私の活動を見ていてくださったGDP副ディレクターで文化人類学の准教授、鄭幸子 Chung Haeng-jaさんから、英語ならなんでもいいのでやってみませんか? とお声がけをいただき、人生初の連続した大学の講義を受け持つことになりました。
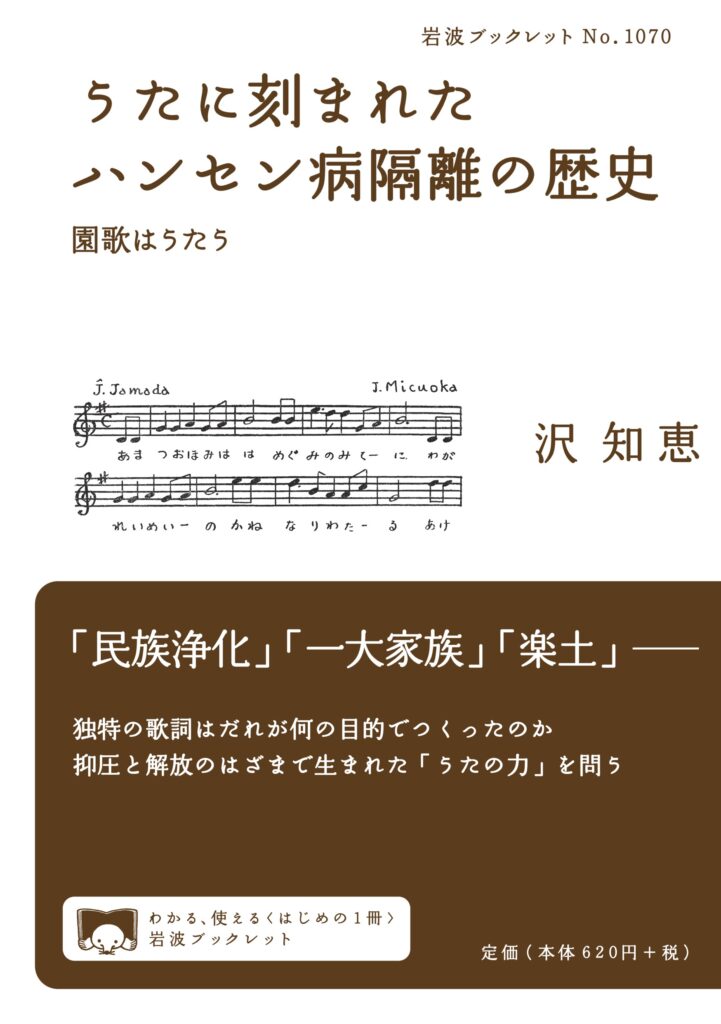
2024年度は約50人、25年度は約60人が履修しました。半数以上が留学生で、ロシア、アメリカ、マレーシア、中国、台湾、フランス、ミャンマー、ベルギー、韓国、ベトナム、インドネシア、フィリピン、タイ、モンゴル、ナイジェリア、トルコなど、生まれ育った国はさまざまです。国内生も含め、英語で講義を受けられることが前提です。学年も専攻もバラバラです。
まず、講義名を「音楽の力 Power of Music」ではなく「音楽と力 Music and Power」とした私の意図について考えてもらいました。どうちがう? 音楽に力があることは、みんなわかっています。「力」とは何か。どのような力があるのか。どのようなベクトルで力が音楽に作用するのか。音楽をただ楽しいもの、気分を上げてくれるものと思っている学生が多かったようで、キョトンとしていました。音楽学という学問があること、音楽は人間のあらゆる側面を映し出すから、それをひとつひとつひもとくことで、「人間とは何か」を問うことができるすばらしい学問であることを語りました。あつく、あつく。
つづいて、「研究もする歌手」である私について知ってもらおうと、RSKTVドキュメンタリー「沢知恵 私は闘いたい―「隔離と歌」の旅」の英語版を見てもらいました。オリジナルの日本語版とあわせてリンクします。
日本語版 https://www.youtube.com/watch?v=LwKu6aXtb3k
英語版 https://www.youtube.com/watch?v=jQD_xM3zbRc
2回目はジョン・ウィリアムズの映画音楽と北朝鮮の音楽です。映画『ジョーズ』のテーマでくり返される短2度、『スター・ウォーズ』の完全五度などをみんなで声を出してうたい、印象を語り合いました。教室には毎回キーボードを持ち込みました。短2度、こわ~い! でも、豆腐屋のラッパの短2度はこわくないね、など、音程やリズムが人の情動に及ぼす効果について感じてもらい、北朝鮮の音楽政策に突入しました。いわゆるサビは6度か8度の跳躍が多いこと。行進曲調の4拍子が多く、付点が多用されていること。高い声でうたうことが求められ、低音の楽器は改良されたこと。卒業論文で北朝鮮のイデオロギーと音楽について書いたとき、家で北朝鮮の名曲集にある全600曲を1節ずつうたってみたら、魂を持っていかれそうになった話もしました。
3回目は《君が代》と唱歌教育についてです。《君が代》が成立した経緯を話すと、国内生たちは目を丸くしていました。何も知らなかった、意味も考えずにうたってきた、と。留学生たちは、えらくゆっくりした短い国歌に新鮮味を感じたようです。唱歌教育について解説したあとには、歌詞にアルファベットをふり、みんなで《故郷》をうたいました。国内生たちが「ノスタルジアを感じた」と口々にいうので、「ノスタルジアって、危ういことない?」と問いかけました。そして、1998年に韓国で日本の大衆文化が開放され、日本国籍を持つ歌手として、私が戦後初めて日本語でうたうことがゆるされたとき、《故郷》をうたった話をしました。植民地時代に日本のうたをうたわされた世代の人たちが、客席でいっしょに口ずさんでくれたのです。「日本語ってきれいだね」と楽屋まで来て伝えてくださった老紳士の話も。2001年にピョンヤンでうたったときは、人民がわかる言語、すなわち朝鮮語(韓国語)でうたわないでほしい、と当局からいわれました。私は幼少時期に韓国で育ち、韓国語ができますが、あの日は日本語と英語でうたいました。北も南も、音楽の力、そして音楽と力の関係をよくわかっている国であるというと、みんな深くうなずきました。
4回目からは、ハンセン病療養所の音楽です。時代背景と隔離の歴史の説明に時間を割きました。日本の近代を知っておくことは、現代の日本について考えるうえで欠かせないことを強調しました。
5回目以降は、学生たちからの提案で、授業の冒頭にそれぞれの国歌、校歌について発表してもらうことになりました。実際にうたってくれた学生もいて、どのような姿勢で、どのような声のトーンでうたうのか、リアルに体験することができました。ミャンマーの学生が数人でうたったときは、不覚にも私は嗚咽してしまいました。政治体制が不安定な中、帰ることができない祖国への思いが、うたを通して伝わってきたからです。あなたたちは歴史の延長を生きている、と感謝と敬意をこめていいました。
全国13か所のハンセン病療養所で共通してうたわれた貞明皇太后の御歌《つれづれの》には、山田耕筰と本居長世が付した別曲が存在します。両方を私の生演奏できいてもらいました。「軍歌王」だった山田よりも軍歌をつくらなかった本居の生き方に共感するが、曲は山田のほうにひかれるという戸惑いの反応がありました。そこで6回目の授業で、私は2枚の絵画を見せました。絵からどのような印象を受けるか話し合ってもらったあと、黒板に作者の名前を書きました。「Adolf Hitlerアドルフ・ヒトラー」。どよめきがおこりました。「さあ、もう一度見てください。印象は変わりますか?」上手に描かれていて心が安らぐと感じた人がほとんどだったようで、みんな大きなショックを受けていました。ヒトラーは美大受験に二度失敗し、夢破れたのです。もしヒトラーが美術家になっていたら、世界の歴史は……。作家と作品の関係について、休み時間返上でディスカッションがつづきました。
7回目は、各ハンセン病療養所の園歌を実演しながらの解説です。「民族浄化」「一大家族」などの歌詞を明るいメロディーにのせてうたわせました。上から押しつけられたそれらのうたは、いま80代、90代の入所者たちによって、「なつかしのメロディー」としてうたい継がれています。二重の意識を持たざるを得なかった権力構造について考えました。

GDPの学生たちと。中央通路の真ん中に座っているのが筆者
最終回は、アフリカ系アメリカ人の音楽について概要を説明し、みんなで立って《聖者の行進》をうたいました。一度うたってから、「ニューオーリンズのお葬式でうたわれたのよ」といったら、またどよめきがおこりました。最後にもう一度うたったときは、大合唱になりました。
「これからはただ楽しむだけではなく、音楽について考えるようになるだろう」。多くの学生が最後にそうコメントしてくれました。自分の生きづらさを、抑圧されたにもかかわらず、うたうことで解放を希求した人たちに重ね合わせた学生もいました。音楽を専門としない学生たちが音楽学に出会うことは、意義のあることです。日本を含め世界のあちこちで「排外主義」が進み、大学に外国からの学生が増えることを問題視する発言もありますが、私の実感は逆でした。多文化主義を声高に叫ばずとも、多様な背景をもつ者が出会い、音楽について対話することで相対化が生まれます。大きな希望を与えられました。
岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラムのサイト
https://discovery.okayama-u.ac.jp/j
(さわ ともえ/西日本支部)